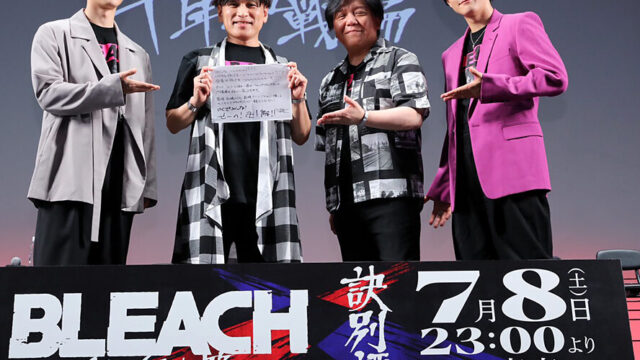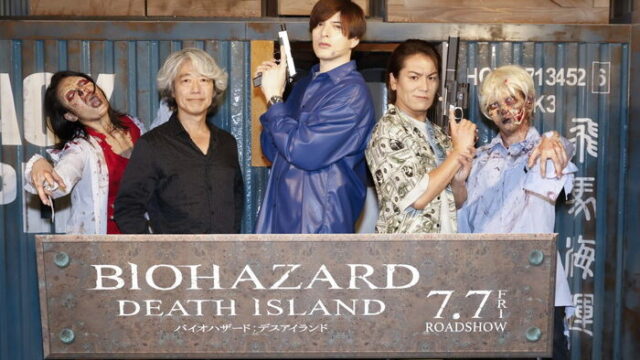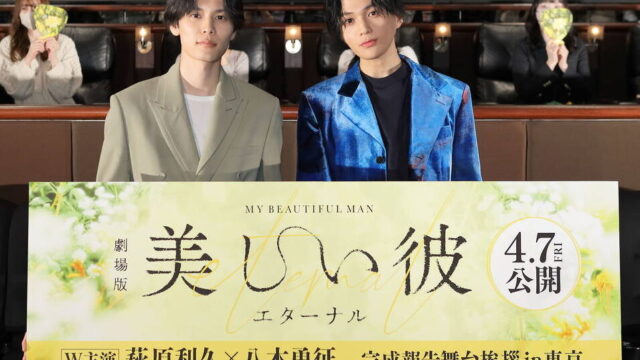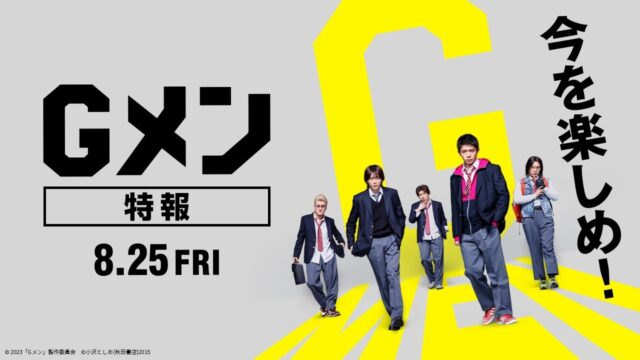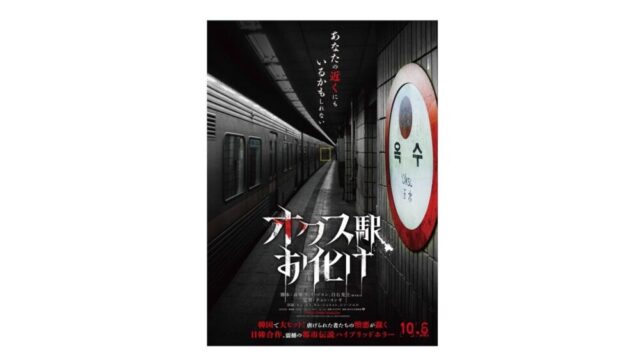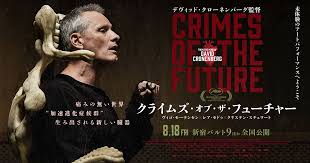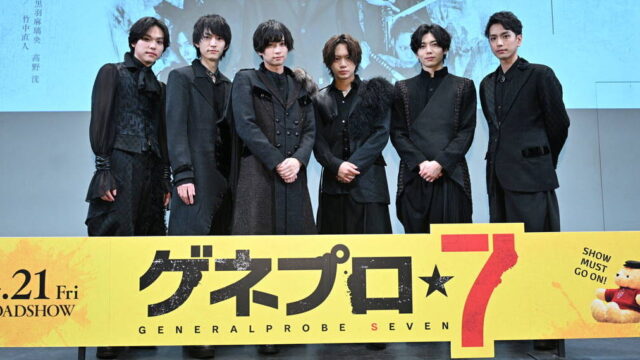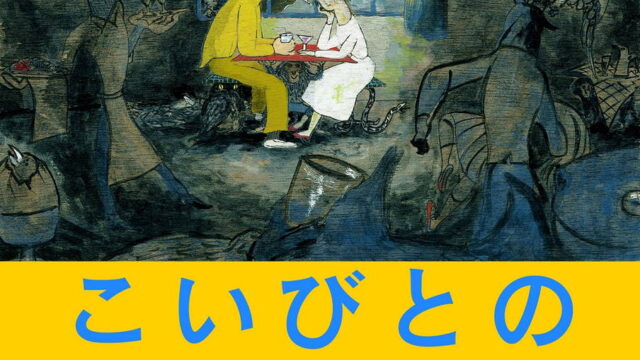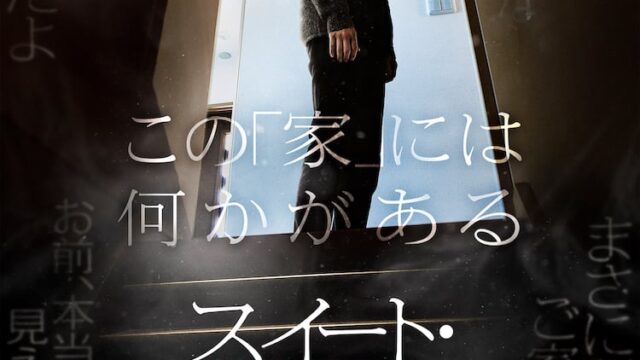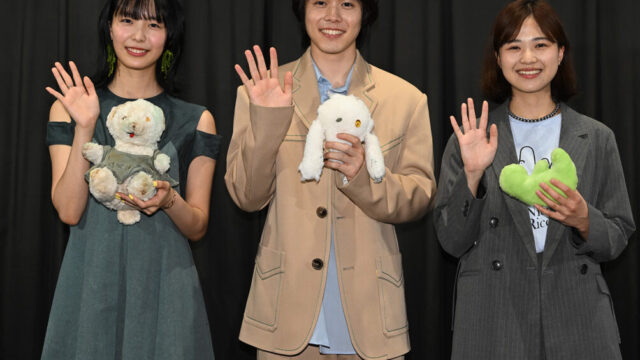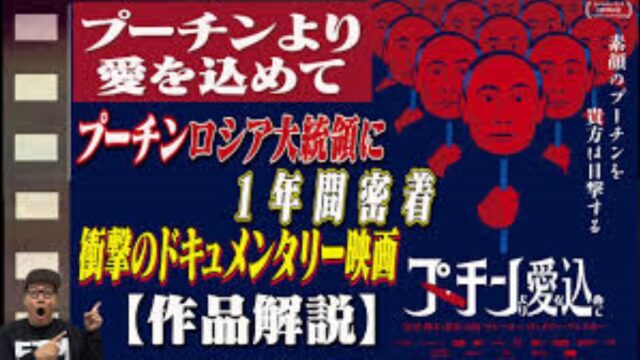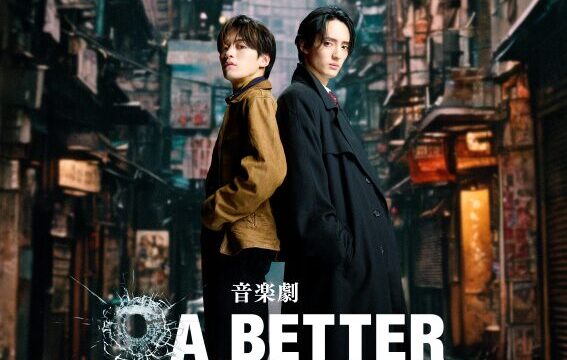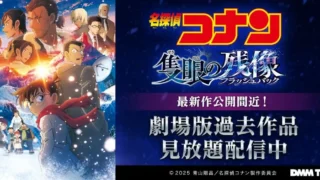今回のウィーン国立歌劇場による日本公演は、2016年以来約9年ぶりの開催となる。演目には、同劇場の代表的なレパートリーである《フィガロの結婚》および《ばらの騎士》が選ばれており、東京文化会館を会場として上演される。同館は今後改修工事に入る予定であるため、今回が休館前最後の大規模な「引っ越し公演」となる見通しである。
今回の公演に関連し、アンバサダーを務める中谷美紀は2018年11月、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団およびウィーン国立歌劇場管弦楽団に所属するヴィオラ奏者、ティロ・フェヒナー氏との結婚を発表している。
中谷さんは子どもの頃からクラシック音楽に親しみを持っていたものの、演奏の経験は限られていると述べており、楽譜の読解にも苦手意識があることを率直に明かしている。そのうえで、オペラに対して「難しい」という印象を抱く観客もいるかもしれないが、より気軽に足を運んでもらえるような親しみやすい芸術であってほしいと語り、自身も一人のファンとしてその魅力を広く伝えていきたいとの意向を示している。
《フィガロの結婚》は10月5日から12日まで、《ばらの騎士》は10月20日から26日まで、いずれも東京文化会館にて上演予定である。
オーストリアと日本の2つの国を行き来しながら活動を続けている中谷さんは、日々の生活の中で劇場やホールに足を運ぶことが自然な習慣となっており、その様子をSNSでも積極的に発信している。これまでミラノやベルリン、ニューヨーク、パリなど、数々の名門劇場に触れてきた彼女だが、特にウィーン国立歌劇場での体験には、心を動かされる特別な思いがあるという。
なかでも、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によるオペラでの演奏は、通常のコンサートでは味わえない魅力があると感じている。壮大なシンフォニーを奏でる彼らが、オペラの舞台ではあくまで控えめに、歌手の息遣いに寄り添って音楽を支える姿勢に深い感動を覚えると語る。
こうした確かな音楽づくりがあるからこそ、世界中の一流アーティストがこの劇場に魅力を感じ、舞台に立ちたいと願うのではないかと中谷さんは思いを伝えました。

帰国を間近に控えた中谷さんは、日本公演に出演する友人、ソプラノ歌手のハンナ=エリザベット・ミュラー(《フィガロの結婚》のアルマヴィーヴァ伯爵夫人役)に誘われ、バリー・コスキー演出による《フィガロの結婚》を鑑賞した。
中谷は、今回上演される《ばらの騎士》と《フィガロの結婚》の2作品について、「まるでミュージカルや宝塚、さらにはストレートプレイの要素も混ざり合ったような舞台」と表現。笑いや感動が詰まった、わかりやすくも深みのある内容が印象に残ったという。
とくに《フィガロの結婚》は、18世紀にモーツァルトが作曲したにもかかわらず、現代の人間関係や社会を映し出すような側面もあり、男女のすれ違いや駆け引きがユーモラスかつ鋭く描かれている。観るたびに心を動かされ、自分自身を振り返る時間にもなったと語っている。

《ばらの騎士》は、2024年1月に亡くなった演出家オットー・シェンクによって1968年に初演された舞台で、それ以来50年以上にわたり変わらぬ形で上演され続けています。日本では、1994年にカルロス・クライバーが指揮を務めた公演によって広く知られるようになりました。中谷さんは、6月にウィーンで行われるこの舞台を鑑賞し、現地からレポートを届ける予定です。
長い歴史を持つこの作品は、移り変わる時代の中で、クラシック音楽の伝統や芸術の継承というテーマを象徴的に語りかけてくれる舞台でもあります。中谷は、「オペラが時代遅れと見なされることもある」としたうえで、それでもなお作品を届け続けようとする表現者たちの熱意に、深い敬意を示しています。
また彼女は、オペラの舞台を「勝敗のないオリンピック」と形容。歌手たちが極限の声で表現に挑み、いつかその声が失われるかもしれないという緊張感の中で、儚くも美しい一瞬を生み出していることに強く心を動かされたといいます。AI技術の発展が進む今だからこそ、今しか聴けない“生の歌声”を体験してほしいと呼びかけています。
 ウィーン国立歌劇場による今回の日本公演は、東京文化会館が改修工事に入る前、最後の本格的な「オペラ引っ越し公演」となります。同館を拠点とする財団は、1974年から海外の一流劇場を日本に招聘し、本格的なオペラ公演を継続してきました。しかし近年、東京近郊では大規模なオペラ公演を開催できる会場が限られてきており、この問題が徐々に深刻化しています。
ウィーン国立歌劇場による今回の日本公演は、東京文化会館が改修工事に入る前、最後の本格的な「オペラ引っ越し公演」となります。同館を拠点とする財団は、1974年から海外の一流劇場を日本に招聘し、本格的なオペラ公演を継続してきました。しかし近年、東京近郊では大規模なオペラ公演を開催できる会場が限られてきており、この問題が徐々に深刻化しています。
今回は例年に比べ、使用される会場が東京文化会館のみに絞られました。この文化会館も今後3年間の改修期間に入る予定であり、その間、同規模のオペラ公演が首都圏で実施できる会場がほとんどない状況になります。
このような現状について、財団の髙橋専務理事は、韓国や中国では新しい劇場の建設が進み、文化政策の後押しもある中、日本では劇場整備が遅れているのではないかと懸念を示しています。オペラのように長期的な準備と専門的な舞台環境が必要な芸術にとって、安定して公演が行える場所の確保は欠かせない要素です。今後も質の高い公演を届けていくためには、こうしたインフラ整備の必要性を広く共有することが重要だとしています。