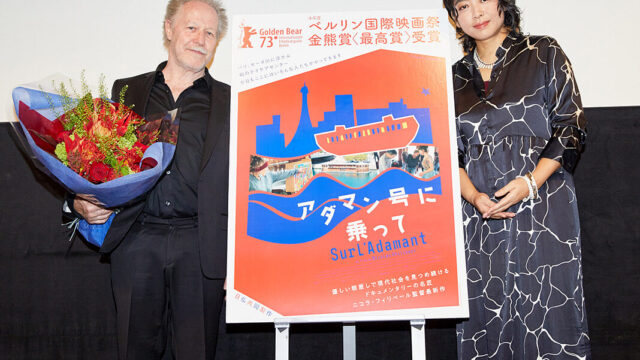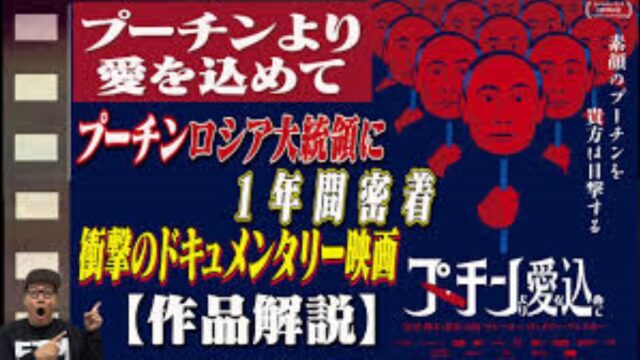2024年11月22日より劇場公開される、日本国内のみならずスペイン、シンガポールから集結した新進気鋭のスタッフ・クルーで製作された国際共同製作映画「カオルの葬式」から、新たな場面写真が公開された。
岡山県北にある宝樹寺をメインの舞台に、わずかに残る古来から伝わる葬儀と、今を生きる人々の姿を描いた本作。場面写真では、大ゲンカが起こる無秩序な葬儀、泣き崩れる喪主、猛スピードで走る霊柩車に加え、過去のカオルの幸せな日常風景などが捉えられている。





 「カオルの葬式」は、”死”をテーマにしたダーク・コメディ。物語は、カオルという女性脚本家が亡くなったという知らせを、10年前に離婚した元夫の横谷が受けるところから始まる。彼女が残した遺言には、横谷がカオルの葬式の喪主になるようにと記されていた。横谷が東京からカオルの故郷・岡山に到着すると、そこに居たのはカオルが遺した9才の一人娘・薫だった。ほかにも、脚本家だったカオルのマネージャー、プロデューサーの先輩や親友、葬儀を取り仕切る婦人会や地主一家など、一クセも二クセもある人々が通夜・葬儀に集まってくる。
「カオルの葬式」は、”死”をテーマにしたダーク・コメディ。物語は、カオルという女性脚本家が亡くなったという知らせを、10年前に離婚した元夫の横谷が受けるところから始まる。彼女が残した遺言には、横谷がカオルの葬式の喪主になるようにと記されていた。横谷が東京からカオルの故郷・岡山に到着すると、そこに居たのはカオルが遺した9才の一人娘・薫だった。ほかにも、脚本家だったカオルのマネージャー、プロデューサーの先輩や親友、葬儀を取り仕切る婦人会や地主一家など、一クセも二クセもある人々が通夜・葬儀に集まってくる。
監督は、多くのドラマ演出・プロデュースを手がけ、短編映画「空っぽの渦」で多くの国際映画祭にノミネートされた湯浅典子。カオル役に一木香乃、元夫・横谷役に関幸治、薫の一人娘・カオル役に新津ちせが顔をそろえ、原田大二郎、黒沢あすか、足立智充、田中モエ、滝沢めぐみ、川島潤哉、蔵本康文、木村知貴、大岩主弥、錫木うりらが出演する。また、音楽監督にジョアン・ビラ、撮影監督にビクター・カタラ、照明にポール・ピーティクス、サウンド・エディターにギエルモ・ルーファス、オフライン編集にマルク・ミチャをスペインから迎えている。
一足先に本作を鑑賞した著名人らによるコメントも公開された。コメントは以下の通り。
【コメント】
■佐野史郎 / 俳優
怖い…怖い映画だ…家族の物語が、いや、物語というものは、本当に恐ろしいものだとジワジワと沁みてくる。けれど、その恐ろしさにまた、癒やされもする。恐ろしさなしには生きていけない。映画は恐ろしい。
■清水崇 / 映画監督
観客は、見知らぬ他人の葬儀に居合わせ、参列させられる。そんな映画、面白いのか?
…ところが……だ。余計な説明や台詞は一切無いまま、個々の人物像や関係性が透けてくる。
人間観察の中で個々の悲哀や哀切、心の距離が量られていく ……『blank13』以来の不思議な映画だ。
そしてエンドクレジットでは、そっと手を合わせ、カオルを偲びたくなる。
■有森裕子 / 元プロマラソン選手
「カオル」と言う1人の女性の死から、いろいろな角度でつながった一人ひとりの「過去、現在、未来」の「生きる」について気づき、考え、光をさしていこう…とする複雑かつ不謹慎ながら面白さを交えて、どこかその姿は新鮮で身近に感じさせる。
■暉峻創三 / 映画批評家( 「ASIAN POPS MAGAZINE」172号より抜粋)
カオルの過去と死後の現在を往還しながら、人の悲劇が招き寄せる喜劇性を浮き彫りにした脚本が、まず独創的で素晴らしい。日本人たちのドラマでありながら、稀有な国際的制作体制が実現。これが本作に、まったく湿り気を感じさせない乾いたタッチと、低予算感を微塵も匂わせないアーティスティックでゴージャスな風格をもたらした。カオル役を演じた一木香乃の魅惑的なキャラクター表現も、作品を強力に牽引する。
■ゲオルク・シュナイダー / JAPANNUAL – ウィーン日本映画祭
湯浅典子監督は、葬儀の場で故人に対して背反する立場の衝突を描いている。遺された者たちはそれぞれ冷ややかな態度から制御不能な感情を爆発させる者まで、さまざまな振る舞いを見せ、不条理でありながら滑稽な場面が次々と展開される。彼らが故人に対して抱く固定観念や記憶は、実際の人物像とおそらく違うだろう。こうした異なる立場の対立は、爆発的なダイナミズムを生み出し、それがコミカルな形で放出される。物語の中で悲劇的要素と喜劇的要素を自在に切り替えながら、回想シーンを巧みに挿入し、悲しみと記憶というテーマに対して、非常に印象的な解釈を示している。
■那須太郎 / TARO NASU代表 ギャラリスト
この映画は複数の人間と彼らそれぞれの時間の交錯をドラマにしていて、リアルでありながらシュールレアリスティックですが、葬式というものの本質もそうなのかもしれません。地方色豊かな背景と普遍的な人間の営みの鮮やかな対比が印象的です。
■いまおかしんじ / 映画監督 カオルは変な女の人だ。セックスの最中でも思いついたら裸のままシナリオを書き始める。男に抱きついて、嬉しすぎてありえへんくらい足を広げてくるくる回る。怒ったり泣いたり笑ったり忙しい。正直メンドクサイ女だ。でもなんか愛おしい。別れても女が死んでも男はそれをずっと覚えてる。
■金子雅和 / 映画監督
黒澤明監督『生きる』後半部のように、不在の人物=死者を巡りそれぞれの人間性があからさまになっていく。おかしみと共に滲み出るのは、ままならない浮き世のもどかしさか。 作品内で脚本家に「オリジナル企画は成立しない」といった言葉が投げられるが、正にオリジナル企画がなかなか撮れない死の海のような日本映画界に、湯浅監督は長年の情熱を保ち続け国際的なクルーと共に、新しい映画の命へ繋がっていくであろう希望の灰を撒いた。
■坂田和也 / 小田急電鉄(株)【XR体験施設】NEUU企画運営担当
日本のものづくりの作品を世界へ発信していく、その意志と取り組みの規模感に感銘を受けるとともに、没入感のある作品づくりについての新たな発見があった。 日常の中にある音(無駄に感じるような音も含めて)が、ハプティクスデバイスがなくても、リズムで同期させることができるという点に深く共感。映画の中に自分がいるような感覚を味わえる、まさに空気感を感じられる映画だ。
■中嶋清美 / (公社)映像文化製作者連盟理事
どんなに親しい人でもその人の全てがわかるわけではない。亡くなった女性脚本家 カオルの通夜の大騒ぎと並行して、彼女の半生が回想され、徐々に明らかになる。がむしゃらに自分らしく生きたカオル。予期せぬカットに切り替わる飛躍もあるが、岡山の葬儀の風習などはしっかり見せる。 “泥合戦”を経て喪主を務めた元夫と彼女の残した一人娘の心が通い合い、最後は救われる。激しく切なく面白く、人が生きるとは何かを問いかける映画である。
■増當竜也 / 映画文筆
通夜から葬儀にかけて、故人に対して容赦なくぶつけられていく愛憎こもごもの感情。果たして本当のカオルはどんな女だったのか?安易な説明を廃して観客一人一人の判断に委ねることで、人間の複雑怪奇な心情を前向きに捉えた見事なエンタテインメント!
■谷口恒平 / 映画監督
関幸治の目には、色気がある。哀愁がある。そして、どこかその場を不穏にさせる力がある。映画は、そんな関演じる喪主のまなざしによって進んでいく。物言わぬ喪主は何を思うのか。何を見ているのか。その目からこぼれる涙が映し出された時、いつの間にかカオルを「分かりたい」と思っていた自分に気づいた。
■西島新 / 新宿武蔵野館 番組編成担当
カオルと過去に関わった人たち、直近まで関わっていた人たち、どちらもカオルとの時間と、その後や“今”生きている時間が存在し、それらを経た彼らの中のカオルの話が通夜で飛び交い炸裂するが、真剣なやりとりほど傍から見ていると滑稽で笑えてしまうことがある。まさにそれを正しくシュールにエンタメに昇華した作品でした。ずっと気になっていた“あの人”も最後の最後できちんと回収されていて思わず一笑。
■小坂 誠/ 第七藝術劇場 支配人/扇町キネマ 映画プログラム編成パートナー
美しく、パワフル!国際共同製作でジャンルレスな凄まじい一作の登場です。
亡くなった人のことを真に理解するのは難しい。暴力的なまでに日常に挿入される葬式というひとときは、その断片的な記憶を手繰りよせ、残された者たちの中に再び生まれ落ちるための儀式のように感じました。
脚本家・カオルの最後のキャスティングは世界をどう変えるのか、見届けてください。

【作品情報】
カオルの葬式
2024年11月22日(金)より、新宿武蔵野館ほか全国順次公開
配給:ムービー・アクト・プロジェクト
© PKFP PARTNERS LLC.