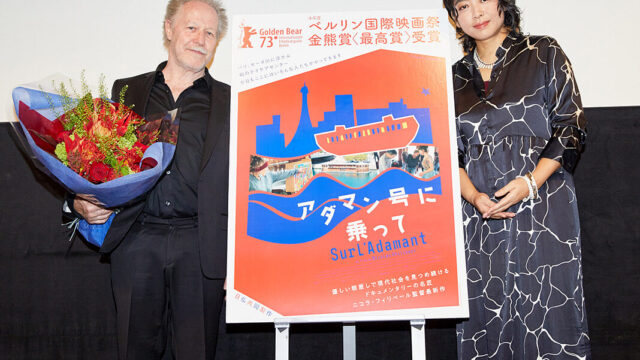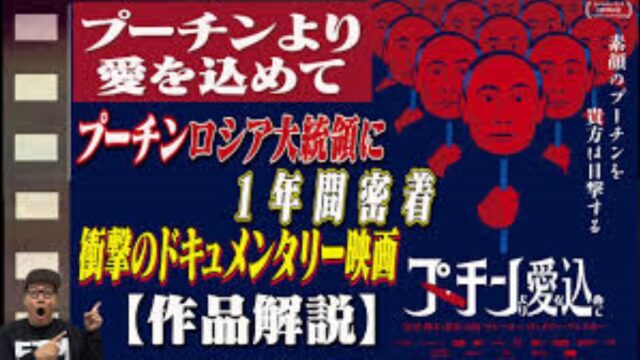2024年10月12日より劇場公開される、七里圭監督、井之脇海主演の映画「ピアニストを待ちながら」から、WEB限定のビジュアルが公開された。
ビジュアルは、井之脇海演じる瞬介と木竜麻生演じる貴織が隣り合い、眠りにつくロマンチックなシチュエーションを収めた、恋愛要素の強いデザインとなっている。
「ピアニストを待ちながら」は、真夜中の図書館で目を覚ました瞬介を主人公とした作品。なぜか外に出られぬまま、旧友の行人、貴織と再会する瞬介。学生時代に演劇仲間だった3人は、かつて上演できなかった芝居の稽古を始める。それは行人が作・演するはずだった「ピアニストを待ちながら」だった。
| 監督は、今年デビュー20周年を迎える七里圭。劇場初作品の『のんきな姉さん』(04)で注目され、カルト的な人気を誇る『眠り姫』(07/サラウンドリマスター版16)や『DUBHOUSE』(12)、「音から作る映画」プロジェクト(14〜18)、『背 吉増剛造×空間現代』(22)など、常に先鋭的な作品を生み出してきた異才である。唯一無二のフィルモグラフィーを重ねる七里にとって、本作は久々の劇映画となる。
|
「のんきな姉さん」でデビュー後、「眠り姫」「背 吉増剛造×空間現代」などを撮り、今年デビュー20周年を迎えた七里圭が、世界的な建築家・隈研吾が手掛けた村上春樹ライブラリーの館内で全編撮影した最新作。2022年10月に早稲田大学で45分版が初披露され、翌2023年1月に舞台あいさつ付きで特別上映されたが、このたび61分の劇場公開版として生まれ変わった。瞬介を演じたのは井之脇海。瞬介の大学の同級生・貴織役を木竜麻生が演じるほか、大友一生、澁谷麻美、斉藤陽一郎も出演している。
本作を一足先に鑑賞した著名人によるコメントも公開された。コメントは以下の通り。
【コメント】
■小川あん(俳優)
村上春樹ライブラリーにわたしは度々、足を運ぶ。そこでは、あらゆる本が息を潜めている。壁に描かれている“羊男”さんが動き出しそうに思える。
グランドピアノからは“巡礼の年”の旋律がきこえる気がする。ここは真夜中になれば、“世界の終わりの図書館”へと姿を変えるのだろう。
——しかし、いつの間にか映画の世界に入り込んでいた。
わたしは、トリガーを探す。
夜更け、本棚に挟まれた中央階段で目覚めた井之脇さんと共に、建物内を彷徨い、静かに歩みを進める。
不確かな存在と演劇が解釈をさらに曖昧にしてしまう。
信じられることは、彼の無欲な表情。この世界が非現実であることを認識する唯一の手がかりだ。
この迷宮から外へ出るには、自分の影を探さなければいけない。
影と合流して、光が差すこちら側へ通り抜けることができたら、また村上春樹ライブラリーを訪れてみて欲しい。
“ピアニストを待つ” 住人がいる、あちら側の世界にまた戻りたくなるだろう。
■上條葉月(字幕翻訳者)
ピアニストの不在が、村上春樹ライブラリーという鍵盤を叩くように、5人にリズムを刻ませる。過去の演劇と同じ言葉や身振りの反復が際立たせるのはむしろ反復不可能な時間の経過。
変わってしまったもの、存在しないはずのもの。
ブニュエル『皆殺しの天使』のように、過去を”演じ直す”ことで何かが変わるかもしれない。
しかし現前しないものの存在を疑うのなら、画面の外に世界はそもそも存在しているのだろうか?確かなことは、ここに奇妙で魅力的な演奏が存在するということだけだ。
■佐々木敦(著述家)
謎めいたタイトルの所以は、映画を観れば多少とも解明される(?)のだが、それ以前に、こう考えてみればよい。
ゴドーを撃て。
これはそういう映画である。
■佐々木誠(映画監督)
映画と小説・演劇・建築の邂逅、その物語性とメタ構造を軸に、生と死、光と影をめぐる難解なミステリーとして、己と向き合いながら観るのが本作の醍醐味。なんだけど、頭からっぽで、ただただ不条理の迷宮を彷徨う快楽に浸るのも楽しい。七里監督作品は、そうやって毎回違う角度から味わえるので、何度も足を運んでしまう。
■柴田元幸(米文学者・翻訳家)
「気づいたら、ここにいて……」「みんなそうだ。だから待つんだよ」――これが自分の物語でない人などいるだろうか。
■渋谷哲也(日本大学教授/ドイツ映画研究)
心にどうしようもない闇を抱えた人たち。神の赦しを待ちながらもそれは決してやってこない。おずおずと演じられる絶望のピアノとダンス。こんな不穏で不条理なドラマが表面上はとても軽やかに展開してゆく。
館に集められた人々が外に出られず姿を消してゆく設定は『そして誰もいなくなった』を思い出した。この映画まだまだ序の口なのだ。その後を想像するのが怖い。
■スージー鈴木(音楽評論家)
早稲田大学国際文学館は、昔の4号館。
半世紀以上前、怒れる若者たちが、何かを待っていた。
40年ほど前、怒り方すら知らない私が、何かを待っていた。
そして今、瞬介たちが、何かを待っている――。
そう。時代は変われど、あの場所で若者は、待ちぼうけを学ぶのだ。
■須藤健太郎(映画批評家)
ピアノが弾けてもピアニストにはなれない。ピアニストと呼ばれる人がピアニストだからである。
演出の経験がなくても、演出家になることができる。演出家に指名されれば、その人が演出家だからである。
大事なのは内実か、それとも名称か。
七里圭はコロナ禍を経た日本の現在に普遍論争の末裔を呼び出し、それを映画の問いとして引き受けた。
――のだろうか?
■田原総一朗(ジャーナリスト)
難しい映画だが、学生や若者たちが感じている社会の閉塞感を見事に表現していた。
もっと自由に、もっと前向きに生きていいんだということを彼らには伝えたい。
■筒井武文(映画監督)
45分版と同じ素材を使っていながら、まるで初めて見る映画になっている、『ピアニストを待ちながら』61分版。圧倒的な音響効果にもよるが、編集の魔術としか言いようがない。演技と台詞と編集が渾然一体となって、この未曾有の映画体験を導いていく。これは前衛主義者には撮れない。古典的な演出を体得した者が、つながるか、つながらないかの綱渡りを演じた結果、現れた(超現実)世界だ。七里圭、恐るべし!
■遠山純生(映画評論家)
俯瞰でとらえられた、ピアノの鍵盤めいて見える階段のうえで目覚めた青年は、ドアを出たところから先へは進むことができない。やがてこの結界、というか境域のなかに閉じ込められた、彼を含む全部で五人の男女が、ピアニストを待つ人々をめぐる奇妙な振りつけの観念的でユーモラスな芝居の稽古に励みながら、ピアニストの到来を待ち続ける。待つことと演じることがループするこの世界では、建物を取り囲むガラスが一種の限界と化して、内と外を遮断しつつ透過させる。既存の建築空間がまるで特別誂えのセットのごとく機能し始めると共に、ガラスに反映/透過されて二重化したり輪郭がぼやけたりしてその存在があやふやになる彼らは、夜が明けることが決してないというこの黄泉のごとき「期待」という名の境域の「外の中で生きる」のだし、「いるのにいなかったり、いないのにいるように思わされたり」する。表が裏で裏が表の、このメビウスの輪を断ち切ることは果たしてできるのか?
■藤井光(美術家・映像作家)
東京国立近代美術館のコミッションワークで私は隈研吾の建築を映像化したことがある。ただし、建築の外観は撮影していない。そこには興味はなかった。それでも建物の内部で繰り広げられる人々の社会的・機能的・資本主義的コミュニケーションの場としての建築には関心を抱いた。結果として、そこで活動する人々の「いま」にカメラの焦点を合わせ、建築の構造体は背景へと退いていく。私にとってそれが隈研吾の建築を撮ることだった。七里圭の映画もまた建物の外観を映さずに、その内部にいる人間にカメラを向けるという意味で、私たちの隈建築の理解は親和性があると思う。ドアのある場所では人は移動し、本を読むことが想定された階段では立ち止まり、物を食べる場所では物を食べ、ピアノのある場所ではピアノを弾く。人間のビヘイビアは空間によりデザインされ、あらかじめプログラムされた規範的な行動をとるよう建築は触発する。この機能性あるいは「権力」を突き崩し脱構築する方法を私は見出せなかったが、映画《ピアニストを待ちながら》はそれを可能にした。「いま」をさまよう人間が、曲がりくねった道として歩み、立ち止まり、待ち続け、迷いながらも再び自分を見出そうとする、そのような人間性を建築に対峙させたからではない。それすらも建築家は設計できる。それでは、この映画の何が隈建築に孔をあけ、芸術作品として突き抜けたものにしたのか。それは冒頭から耳を澄ませば見えてくる。
■古川日出男(作家)
ここには現代的な状況がシンボリックに描かれていて、それはつまりグローバルな想像力に基づいているはずなのに、しかし七里圭監督作のここには〈日本〉の特異的な想像力もまた深く根を張っている、と自分は鑑賞中にずっと感じていて、それはなぜだったのだろう? 出られない建物(図書館)と明けない夜、との設定をグローバルな想像力からズラして探るに、たとえば江戸時代の国学者にして作家の上田秋成は『雨月物語』内の一篇となる「吉備津の釜」という作品を書いていて、ここでは良妻を裏切って愛人と駆け落ちした男が出る。そして妻は死に、怨み、祟る。その祟りを逃れるためには妻の死後四十九日が過ぎるまで「戸締まりした家に、外には一歩も出ないで、籠もる」ということをしなければならない。ついに四十九日めの夜が過ぎ、ああ窓の外が明けた、夜明けだ!と思って外に出た男は、それは怨霊の企んだ幻術であって実際には夜はぜんぜん明けていなかった、そして・だから大量の血と髪の毛の束だけを残して消える、というのが秋成の「吉備津の釜」なのだが、かつアイディアの原形は中国の短篇小説にあるらしいのだが、上田秋成という激烈な異才によって完全に〈日本〉化されている。そこだ。そこに七里圭『ピアニストを待ちながら』に通ずる何かがある。亡霊の擬装した夜明け、の反転、というよりも千の断片に散ること。ここに七里圭の現代性があり、これはグローバル化の文化状況もパンデミック下とその後の状況も撃っている。そして〈日本〉とは四方の海洋がそのまま国境線とイコールになってしまっている、つまり出られない図書館にほぼ等しい「海に囲われる列島国家」なのであり、その海を夜と考えて待たれ続ける朝でもあるのだと考える時に、この映画の鑑賞体験の「意味」がわずかに光を射される。怖い。
■三浦哲哉(映画研究・批評)
外に出ていったのに、内にいたまま。
終わったのに、終わっていない。
真夜中の図書館は迷宮となり、
サスペンスフルな寓意劇がエンドレスに展開する。
現代映画の最果てを孤独に走る七里圭の魔術的演出は、映画、映像、演劇、図書館、それらの本質的な不可思議さをぬっと浮かび上がらせる。
その気持ちよさ!
■門間雄介(ライター/編集者)
静寂に包まれた夜の図書館では、なにが起きても不思議ではない。
朝がいつまでも訪れず、若者たちはそこに閉じ込められ、あっけにとられるほどの不条理に支配されたとしても。
館外から絶え間なく聞こえてくるのはシュプレヒコール?
そのかすかな叫びは、かつて高名なジャズピアニストが乱入ライブを行った学園紛争の時代へ、わたしたちを誘う。
歴史や、そこに積み重なった知性や教養とのつながりすら得られる、摩訶不思議な映像体験。

監督・脚本:七里圭
プロデューサー:熊野雅恵
撮影:渡邉寿岳
照明:高橋哲也
録音:松野泉 黄 永昌 音楽:宇波拓
編集:宮島竜治 山田佑介
制作・配給:合同会社インディペンデントフィルム
2024年/日本/カラー/61分/ヨーロピアンビスタ/5.1ch /DCP
©合同会社インディペンデントフィルム/早稲田大学国際文学館